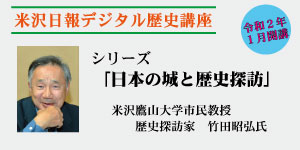|
歴史探訪【板谷街道編】寄稿 竹田昭弘氏
米沢藩の生命線「板谷街道」を想う(2/4)
6 笹木野宿を開いた茂木某
大坂夏の陣で豊臣家は滅んだが、その重臣であった茂木一族が上杉領内、陸奥笹木野に逃げてきた。その茂木某が笹木野に宿場を開いたと言うのである。この新宿場により従来の大森道が使用されなくなった訳である。寛永12年(1635)幕府は、大名や旗本の行動を規制する「武家諸法度」を制定した。
 この頃幕府はこの他に朝廷と公卿を規制する「禁中並びに公家諸法度」、更に寺院を規制する「寺社法度」と相次いで制定し、幕府の体制強化を図っている。江戸幕府による大名統制策は参勤交代・改易転封・縁組規制など多岐にわたった。この「武家諸法度」により参勤交代が義務化されると、諸大名は公用の旅が多くなり、それに伴い完備された宿場と宿駅のある街道が必要になったのである。2代上杉定勝は参勤交代に対応した「道中法度十ヶ条」を制定している。その第一項に"公儀御法度に万事背いてはならぬ"としている。いかに参勤交代制が外様大名にとり、命とりになりかねない法度であったかが分かる。全て藩主は江戸の藩邸に到着すると、その旨を先ず幕府に報告せねばならなかった。上意への謝礼を使者をもって申し述べ、老中に登城の取りなしを依頼した。藩主は江戸城に登営し献上金品を捧げ拝謁して参勤御礼を言上した。退座後は将軍の近親・老中以下に廻謹して贈答品を贈るのが慣例であった。
この頃幕府はこの他に朝廷と公卿を規制する「禁中並びに公家諸法度」、更に寺院を規制する「寺社法度」と相次いで制定し、幕府の体制強化を図っている。江戸幕府による大名統制策は参勤交代・改易転封・縁組規制など多岐にわたった。この「武家諸法度」により参勤交代が義務化されると、諸大名は公用の旅が多くなり、それに伴い完備された宿場と宿駅のある街道が必要になったのである。2代上杉定勝は参勤交代に対応した「道中法度十ヶ条」を制定している。その第一項に"公儀御法度に万事背いてはならぬ"としている。いかに参勤交代制が外様大名にとり、命とりになりかねない法度であったかが分かる。全て藩主は江戸の藩邸に到着すると、その旨を先ず幕府に報告せねばならなかった。上意への謝礼を使者をもって申し述べ、老中に登城の取りなしを依頼した。藩主は江戸城に登営し献上金品を捧げ拝謁して参勤御礼を言上した。退座後は将軍の近親・老中以下に廻謹して贈答品を贈るのが慣例であった。
板谷街道の出羽側の赤浜道が参勤交代に使用されなくなり、代わって大沢を通る間道が新しく参勤交代の街道として改修されると、米沢から関根を経て大沢宿、板谷宿、李平宿、庭坂宿、笹木野宿、そして福島に至る、これが江戸時代に人々に利用された板谷街道の全貌であった。
板谷街道は板谷峠越えが険しく歩くのは楽ではなかった。それでも米沢藩にとり陸奥に抜ける唯一の近道であった。会津街道は藩政時代には供用が困難になっていた。この為に出羽国の諸藩ではこの険しさを嫌い参勤交代には利用しなかったのである。代わりに上の山から金山峠越えで七ヶ宿街道に入り、小坂峠を下り陸奥国伊達郡桑折に出たのである。このことで出羽諸藩の大名達が米沢城下を通行することがなく、板谷街道は専ら米沢藩の専用街道と言ってよかった。上山藩は羽州街道を整備し以北の諸藩の役に立てた。庄内藩は藤島街道から清川街道をとり新庄・楯岡・上山から福島へ、秋田本荘藩は酒田・尾花沢を経て上山から福島へと言う様に小坂峠越えをした。
7 米沢の絹問屋藤倉富蔵が新道を開発
板谷街道の最大の難所は板谷峠の鉢森山の頂上近くを通る道程であった。こうした板谷峠の険しさに耐えられず、米沢の絹問屋藤倉富蔵は、幕末の天保4年(1833)に米沢藩に新道の開発を願いでた。だが藩からの許可は下りなかった。そんな折、暴風雨により街道が壊され通行できなくなった。藤倉は再び願い出てやっと許可が下りた。藤倉は自ら資金集めに奔走し、嘉永元年(1848)に念願の鉢森山の裾を周回する新道を開拓したと言う。頂上近くの道よりかなり下に出来たことで、旅人は楽に通行できる様になったのである。先人の不屈の意志を敬わずにはおられない。
 因みに板谷街道の海抜をみると、関根で約3百米、鉢森山麓で約8百米、国境の産ヶ沢で約4百米、高津森峠で約6百米と上り下りのきつい街道であったことが分かる。そして江戸から米沢までは凡そ83里とある。凡そ330百キロである。その中で福島と米沢間の板谷街道の距離は12里であった。参勤交代は一日に約10里(40キロ)を歩き宿場間を移動した。上杉家の江戸までの日数は当初は概ね6泊7日とされていた。強行軍であったことが分かる。 宿場の機能についてみてみると、宿場では問屋・庄屋・本陣の仕事に就いている者が協力して交通の流れを捌いていた様である。板谷街道の様な脇街道では、この3つの仕事を1人で兼ねる者もいたと言う。宿場の長はその町や村の富豪で名望のある者がその職に就いていた。大沢宿の斉藤氏、李平の安部氏、笹木野の茂木氏などはその代表例である。問屋の仕事は、人馬の指引・休泊の世話・宿場事務の監督などが主なものであった。普通一宿に二人位の問屋職がいた。現代で言えば問屋は運送業かもしれない。
因みに板谷街道の海抜をみると、関根で約3百米、鉢森山麓で約8百米、国境の産ヶ沢で約4百米、高津森峠で約6百米と上り下りのきつい街道であったことが分かる。そして江戸から米沢までは凡そ83里とある。凡そ330百キロである。その中で福島と米沢間の板谷街道の距離は12里であった。参勤交代は一日に約10里(40キロ)を歩き宿場間を移動した。上杉家の江戸までの日数は当初は概ね6泊7日とされていた。強行軍であったことが分かる。 宿場の機能についてみてみると、宿場では問屋・庄屋・本陣の仕事に就いている者が協力して交通の流れを捌いていた様である。板谷街道の様な脇街道では、この3つの仕事を1人で兼ねる者もいたと言う。宿場の長はその町や村の富豪で名望のある者がその職に就いていた。大沢宿の斉藤氏、李平の安部氏、笹木野の茂木氏などはその代表例である。問屋の仕事は、人馬の指引・休泊の世話・宿場事務の監督などが主なものであった。普通一宿に二人位の問屋職がいた。現代で言えば問屋は運送業かもしれない。
又庄屋の仕事は宿場の行政面の長である。本陣は参勤交代に利用する大名や公用で旅をする上級武士達を宿泊させる定宿のことであった。この他に脇本陣や宿御殿などと言う施設もあった。板谷街道の様な主要街道の宿場でも旅籠などが兼業で旅人の世話をしていた。米沢藩では福島の阿武隈川河岸に藩米蔵を建てそこに他領に売る米を運び込んだ。今でも福島市内の阿武隈川河畔の御倉町には米沢藩米蔵が復元されている。そこから阿武隈川を下り宮城県荒浜から海路江戸へと運び米沢藩浜屋敷に入れた。その輸送路として板谷街道が利用されたのは言うまでもない。他に長井の最上川川湊を利用して、酒田から日本海ルートで江戸へ運んだとも言われる。
8 里程の起点となった大町「札の辻」
街道は人の移動だけではなく、情報も出入りし、主なものは物資の輸送が実は最大の役務であった。次に宿場間についてみてみる。
 【大町〜関根間】
【大町〜関根間】
上杉氏が減封され米沢に入部すると、執政直江兼続は早速町作りに着手した。
伊達氏時代の城下城郭は、堀が一重で本丸と二の丸だけであったが上杉氏は新たに外濠を巡らし、三の丸を造成し城下を作りかえた。米沢の上杉氏は四囲を全て敵に囲まれた監視の中にあったと言ってよい。北は山形の最上氏が、東は仙台の伊達氏が、西は越後の堀氏、南は徳川方となった蒲生氏と言う状況であった。それだけに直江の戦備城下の整備は急を要し、万全たる備えが求められた。米沢の出入口には四方に全て枡形の出入口を設けた。南は旧七軒町の枡形、北は旧粡町の枡形、東は旧川井の枡形などが今も顕著に残っている。そして外周には寺町が配された。北寺町・東寺町・南寺町の町並が今も現存する。更にその外側を松川・羽黒川・堀立川・鬼面川の河川が防御の盾となった。戦国はいつ敵に攻められようともあらゆる手立てで防ぎ切る覚悟が無ければ守ることができない。"備えあれば憂いなし"が最優先であった。
この城下整備の時、制札場の「札の辻」を新町に置いた。そこは旧元籠町であった。新町は米穀商人達が住む町であった。市が立てられて、在郷の農民達が集まってきて賑わったと言われる。これが新町から粡町と書く様になったと言う。元和年間に奉行郡代の平林正恒は、「札の辻」を大町の十文字に移した。制札場には制札を掲示した。現在の広報板である。又大沢や板谷などの各宿場にも制札場を設け、大町「札の辻」を里程と宿場の基点とした。大町の十文字は現在の大町の小関洋服店がある十字路である。現在その地は復元されて広場になり制札板が立っている。観光客の為の腰掛も用意されている。案内板もあり、当時の様子もうかがうことができる。
それを見ると、次の如く記されている。"この大町の十字路は江戸時代には米沢城大手門につながる重要な十字路で、米沢領内の街道の基点となった。人の行き交う目立つ場所であった為、幕府や藩の法令を掲げた高札場が設けられた"とある。今も旅人が訪れ往時の面影を偲んでいる。米沢から参勤交代の旅の出発は現在の福田町(当時福田村)を起点とし、大沢宿まで3里3丁(12キロ)の道程であった。松川、白旗松原の白旗八幡宮、関根羽黒神社と行く。当時関根には関所が設けられていた。
9 東町から福田町へ通る板谷街道
大町札の辻を起点として分枝している街道は2本である。だが国境までの街道は、板谷街道が板谷の国境産ヶ沢まで六里五町程、最上街道は国境の掛入石中山まで七里、会津街道は国境の綱木峠まで五里、荒砥街道は国境の萩野中山まで十三里となっていた。分枝しているのは板谷街道と最上街道で、他の街道はこの二本から更に分枝していた。板谷街道は大町札の辻を起点とし、そこからから南に進み、つきあたって左に折れ、直ぐに右に折れて東町へと至った。
東町は町屋敷が並び、問屋、旅籠、店で賑わう城下の入口であった。そこには皇太神社があり以前は神明片町と言っていた。上杉謙信の信仰により神明宮を建立している。
今は寿々木屋蕎麦屋が右手にある。そこから南に向かい平野屋商店があるところを左に折れて福田町へ向かい、更に福田町の現在の芳賀商店から南へ向かうと言うものであった。最上街道は「札の辻」を逆に北に向かい、つきあたると右に折れ川井小路に出る。そこから左に折れて立町に出て突きあたる。そこを右に折れてつきあたり粡町に出る。直ぐに右に折れて枡形に至り、銅屋町、長町、北町と通って山形方面へ向かった。
粡町の枡形には「あかがねや」の家屋が残り、昔を彷彿とさせてくれる。この最上街道を粡町から右に曲がらずまっすぐ進み、信夫町を通り成島町に出て広幡を抜けると小松方面へと続いている。小松から更に二本に分れ荒砥街道と越後街道と分かれていた。荒砥街道は萩の中山から山形方面へ向かうが、越後街道は小国から藩境玉川番所に至り、更に越後へと続いていた。
 平野屋商店あたりは当時、石田名助が問屋を構える東町であった。石田名助は宿場町米沢の輸送問屋であった。石田名助の先祖は関ヶ原の合戦で敗れた石田三成だと言う。石田三成には居城佐和山城に父正継・兄正澄、岳父宇多頼忠ら一族がいたが、合戦の煽りを受けて徳川軍の攻めに遭い落城すると一族が悉く自刃して果てしまった。果たして米沢へ逃げ込んだといわれる者が誰の流れなのか、川西町堀金に三成の三男が直江兼続を頼り米沢に逃げてきて、後に米沢城下に堀金屋と言う問屋を出した。それが後年、身代を大きくして石田名助へと繋がったとも言われる。石田名助は問屋や旅籠の経営の他に、物産会所と東町検断職を持つ実力者であった。物産会所とは織物などの販路開拓や江戸へ輸送したりするもので、現代で言えば商社の様な仕事であった。
平野屋商店あたりは当時、石田名助が問屋を構える東町であった。石田名助は宿場町米沢の輸送問屋であった。石田名助の先祖は関ヶ原の合戦で敗れた石田三成だと言う。石田三成には居城佐和山城に父正継・兄正澄、岳父宇多頼忠ら一族がいたが、合戦の煽りを受けて徳川軍の攻めに遭い落城すると一族が悉く自刃して果てしまった。果たして米沢へ逃げ込んだといわれる者が誰の流れなのか、川西町堀金に三成の三男が直江兼続を頼り米沢に逃げてきて、後に米沢城下に堀金屋と言う問屋を出した。それが後年、身代を大きくして石田名助へと繋がったとも言われる。石田名助は問屋や旅籠の経営の他に、物産会所と東町検断職を持つ実力者であった。物産会所とは織物などの販路開拓や江戸へ輸送したりするもので、現代で言えば商社の様な仕事であった。
10 石田三成の子孫と伝えられる検断石田名助
 検断職とは町名主とか町年寄と呼ばれていて、現代風に言えばその町の町長とかと言われるものだった。当時の米沢の町屋は本町と脇町からなっていた。本町は商人の町で、大町・柳町・立町・東町・粡町・南町の六町で、各々1名の検断がいた。これは伊達氏が仙台に移した町でもある。脇町は職人町や寺町で各町に1名の検断がいるとは限らなかった。一方会津街道は東町の石田名助の問屋のところから分枝していた。東町を南に進み、途中で右に折れて南町に、そして馬口労町にでる。そこから七軒町に出て、関、綱木を経て桧原峠越えで会津に至った。
検断職とは町名主とか町年寄と呼ばれていて、現代風に言えばその町の町長とかと言われるものだった。当時の米沢の町屋は本町と脇町からなっていた。本町は商人の町で、大町・柳町・立町・東町・粡町・南町の六町で、各々1名の検断がいた。これは伊達氏が仙台に移した町でもある。脇町は職人町や寺町で各町に1名の検断がいるとは限らなかった。一方会津街道は東町の石田名助の問屋のところから分枝していた。東町を南に進み、途中で右に折れて南町に、そして馬口労町にでる。そこから七軒町に出て、関、綱木を経て桧原峠越えで会津に至った。
現在、平野商店の十字路から東へ延びる道は直線道路になっていて福田町に至るが、当時はこの直線の道と東寺町から道が交差するところで、鈎形に曲がって枡形を成していた。ここには福田番所、木戸があった。東寺町も米沢城下を守る上で大きな役割をもっていた。 東寺町は文字通り寺院が南北道に沿って配置され、北から南へ順に極楽寺・日朝寺・高岩寺・輪王寺等の巨刹と、その間に多くの小寺院を配して並んでいた。上杉氏が米沢に入部した時、越後などから多くの寺院も移ってきた。東寺町は東から攻めてくる敵の侵入を最初に食い止める防衛線であった。
それは上杉氏が仙道からの伊達氏の侵攻を想定したものであった。因みに北寺町は北から攻めてくる敵を想定したもので、山形の最上氏を意識したものであった。寺院の境内には、直江が考案したとされる万年堂の墓石が上杉独特の石積みとなって並んでいた。敵が板谷街道から攻めてきて関根方向から米沢城下に入ろうとしても、この福田町の枡形に遮られすんなりとは城下に入れなかった。この様な方式は七軒町の枡形、粡町の枡形と同じであった。 板谷街道は更に福田町の芳賀商店から南に折れて現在の吾妻町にでる。途中には福田清水があり、用水として川桶に接ぎ家の中で利用した貴重な水源であった。米沢の城下は町内の各所に町の中央を用水が流れ生活用水としていた。嘗て黒川町では近年までその姿が見られた。板谷街道は途中米坂線の踏切りを渡るが、この辺から南へ少し下り坂になる。この坂を当時は外道坂と呼んでいた。この道は罪人が通る道でもあったのである。罪人は更に道の東側にある小川の中を歩かせられて刑場に連れていかれたと言う。旅人と同じ道を歩かせられないと言うことだったのだろうか。しかも処刑は12月に行われた。